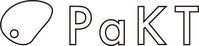About Us
PaKTの語源
フィンランド語の「地域(a)、教(共)育(k)、アート(t)」の頭文字を組み合わせ、「プロジェクト(p)」を行うという意味を込めて、創設当時の大学生がPaKTと名付けました。
- 地 域:alueella
- 教(共)育:koulutus
- ア ー ト:taide
コーポレートロゴ

PaKTはパレットをロゴにしました。
パレットに自分という色を出す。
プロジェクトという真っ白なキャンパスに向かいあなたが描く。仲間と描く。
過程で、学び、気付きを得ていく環境をつくることを目指しています。
PaKTの起源について
世界一と言われたフィンランド教育。それを日本で適応する形で取り入れようとしたのが、2010年のPaKTの起こりです。なぜ、フィンランドは世界一の教育なのか。フィンランド教育の本質を創設者の松榮秀士は、「自然」と「信頼」であると捉えました。エアギターや、凍った池を使ったメリーゴーランド、サウナ文化、マリメッコ、ムーミン。フィンランドは、自然を愛し都市と田舎の2拠点での生活をする人が多いそうです。なにもない自然の中で、空想する。空想はその人だけのものであり、希少性そのもの。しかし、空想では、他者は触れられません。そこで、想像できる状態にします。つまり、企画書に落とし込みます。企画書は現代人の魔法。企画書にして伝えることで、一人の空想を共有することができます。触れられるものになります。そこから実際に形にしていく創造の段階があります。創造とは、感じられるものをツクるということです。自然を起源にした教育は、空想→想像→創造のサイクルを繰り返し、その過程で失敗を繰り返し、反省し力を得るようになります。
信頼とは、目をかけてもらっているという安心感から生まれます。安心安全の環境であるからこそ、人は挑戦できます。深い話をしたり、弱みを打ち明けたりし、共感共有の中から応援が自然発生的に生まれてきます。教育に必要なことは、この信頼がある環境。信頼できるのかどうかを、子どもでも大人でも関係なく、人はみようとします。フィンランド教育の中で、本当かどうかわかりませんが、宿題がないという話を聞いたことがあります。この話を聞いたとき、納得したことを覚えています。それは、勉強をしていないということではありません。目をかけてくれていると安心できる環境がある人は、宿題という形でなくても、努力したいと感じるし、努力したことを伝えたい!と思うはずですから。学ぶとは、挑戦するとは、環境が大切だということです。
PaKTのルール設計の背景
まず最初に取り組んだことは、個人がルールにならないということでした。発想をルールによって自律的に判断できる枠組みを作ることを目指しました。
地域・教育・アートというルール
そこで、PaKTでは「地域」「教育」「アート」の3つの観点をルールとして導入し、それに基づいてプロジェクトの可否を判断するようにしました。これにより、個人がルールになるのではなく、組織全体が一貫した基準を持つことができるようになりました。
地 域:プロジェクトがその地域の文化や価値観に沿っているかどうか。
PaKTでプロジェクトを進める場所や環境は、誰かが思いを込めて作り上げたものであり、その場所に対する「上位概念」に応じて解釈し、行動することが求められます。具体的には、その場所が何のために作られたのか、どんな目的で存在しているのかを理解し、その意図に沿った形でプロジェクトを展開することで、地域に対して応えていると言えるという考え方です。
教(共)育:そのプロジェクトが参加者にとって学びや成長を提供できるかどうか。
プロジェクトに関わる際の学びについても、作り手や参加者が自由に解釈し、定義することが許されています。何を学べるかを言語化し、プロジェクトにおける挑戦や目的を明確にすることで、そのプロジェクトが教育的な価値を持つように設計できるという視点です。
アート :創造性や感動を呼び起こす要素が含まれているかどうか。
創造性や感動をもたらす要素をどう取り入れるかが重要です。視点を変える、緊張感をデザインするなど創造性が加わるならば、PaKTとしてのルールに沿ったプロジェクトになり得ます。
例えば、ダンボールを積んでバイクで突っ込むような提案は、面白いし、参加者にも工夫する余地があって学びになるが、地域的に×になる。大規模な飲み会の提案は、教育的な価値が見いだせないためにできない。しかし、それぞれのプロジェクトがこれらの3つの基準に適合するならば、自由な発想を基に実行できる余地があるということです。
まとめ
PaKTのルール設計は、参加者の自由な発想を可能にする一方で、それが地域や教育、アートの観点からも整合性があるかを自律的に判断できる仕組みを提供しています。この枠組みにより、プロジェクトが誰か個人の判断に依存することなく、組織としても進めやすい構造が整えられているのが特徴です。日本で受け入れられる形にしようと、3つのルールを決め、その3つをすべて満たしている形で、空想→想像→創造の過程で学ぶサイクルを行う環境がPaKTです。またこの過程で学ぶサイクルを関係性型学習RBL(Relationship Based Learning)と名付けました。
会社の歴史・沿革
2010年 PaKT創設。週1回の勉強会&会議を実施。縦のつながりキャンプ事業をスタートする。
2011年 京都堀川北山にオフィス設置。ほりきた学習教室(代表個人事業として開始)働くことを考えるリクルートキャンプを開始。働くを体感する企業ゲームを自社開発。
2011年 英語劇による英語教育DELP開始。
2012年 2拠点(堀川北山・西院)に拡大
2012年 村・留学事業開始。
2013年 松ヶ崎にオフィス移転。ほりきた学習教室から同一空間型個別指導塾マナビノバへ名称変更。3拠点(出町柳・松ヶ崎・西院)に拡大。
2013年 エコな飲み会Green drinks Kyotoを開始。
2014年 松ヶ崎から下鴨に移転。出町柳撤退。
2016年 PaKTcompany合同会社として法人化。
2016年 パクトハウス事業開始:拡張家族の社会実験開始。
2016年 DELP事業解散。京都文教大学に村・留学の窓口設置(参加者が集まらず、同年撤退)
2016年 村・留学を商標登録
2017年 国際事業開始。中国国立大学へのインターンシップ、中国国立大学へ全額奨学生での留学紹介。日中学生交流会、合宿の運営。
2017年 同志社中学校へ企業ゲームの授業提供。
2019年 西院を事業譲渡。
2019年 Green drinks Kyoto 20回の開催後休止。
2020年 下鴨オフィスの移転。現在の場所へ
2021年 小中高生のための大学院Coda school事業を開始。
2022年 パクトハウス移転。(出町柳から高野)
2023年 摂南大学現代社会学部へ授業提供開始。村・留学が単位認定を受ける。
2023年 立命館中学高等学校へ村・留学奄美大島の授業提供。
2024年 小中高生のための大学院を商標登録
2024年 フォルケホイスコーレ:コウルを設立。
2024年 日本ソーシャルイノベーション学会にて、Codaschoolとして分科会を開催。
2024年 RBLの教科書づくりプロジェクト開始。
2024年 同志社大学で教科書づくりのための正規授業内で社会実験。
クライアント
摂南大学
同志社大学
立命館中学・高等学校
京都市 大学政策課・地域イノベーション推進課
(株)マザーハウス
受賞歴
2016年 京の公共人材大賞知事賞受賞
2021年 京都市地域輝き企業賞
知的財産
商標登録
村・留学(2016)
小中高生のための大学院(2023)